天籟能の会のワークショップでもお世話になっている刀鍛冶、川崎昌平師の工房(道場)に、協賛会員のみなさまとお邪魔してきました。

以下、撮影は金川晋呉さんです。
▼川崎昌平さんの銘

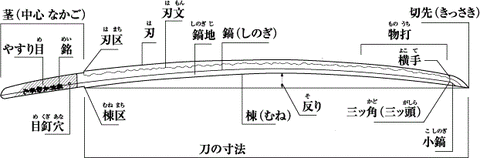






▼試し切り


天籟能の会の協賛会員へのご応募、お待ちしております。
詳しくは、こちらをご覧ください。天籟能の会「協賛会員」のお願い
また、「天籟能の会」、チケットもまだございます。みなさまのご参加をお待ちしております。

以下、撮影は金川晋呉さんです。
▼川崎昌平さんの銘

刃に照明を反射させてると、木目のような模様が見える。
①まず一礼。
②両手で茎(なかご)を持つ。 ※茎…柄に入れる部分
③右手で持って刀身を立て、天井の照明を使って全体の姿を観る。
④水平に持ち替え、照明を反射させて刃の表面を観る。
表は元から切先(きっさき)に向かって、裏は切先から元に向かって観る。
ような模様。
⑥もう一度全体の姿を観る。
⑦枕に戻す。このとき棟(むね)側から着地させ、刃をそっと倒す。 ※棟…刀身の切れない側。
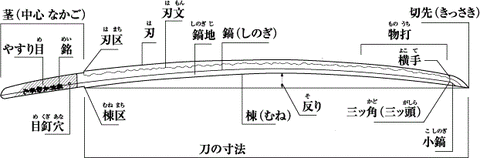
参考画像 瀬戸内市のHP
▼晶平鍛刀道場



炎の温度は1200℃近くまで高温になる。炎と火の粉の色で適温を判断する。
▼「折り返し鍛錬」見学。
「折り返し鍛錬」は、刀を作るなかでもっとも時間のかかる作業。


鋼を何度も折り返しながら鍛えることで、強度を増す。素材にもよるが、打つ、折り返すの作業を6~8回繰り返す。



見学の際はひとりでの作業だったが、通常は向こう槌と呼ばれる相方と打つ。このとき、向こう槌は刀匠の合図に合わせて打つことから、「相槌を打つ」という言葉が生まれた。また、トンテンカン、トンテンカンとリズミカルに音が鳴るはずのところで、向こう槌が打ち損じると音が外れてトンチンカンになるとも。

参加者の「相槌(向こう槌)」体験


鋼を何度も折り返しながら鍛えることで、強度を増す。素材にもよるが、打つ、折り返すの作業を6~8回繰り返す。



見学の際はひとりでの作業だったが、通常は向こう槌と呼ばれる相方と打つ。このとき、向こう槌は刀匠の合図に合わせて打つことから、「相槌を打つ」という言葉が生まれた。また、トンテンカン、トンテンカンとリズミカルに音が鳴るはずのところで、向こう槌が打ち損じると音が外れてトンチンカンになるとも。

参加者の「相槌(向こう槌)」体験
赤松の炭を使用。赤松は火力があり軽くて扱いやすい。また、最後まで形が崩れない。
弟子入りして最初の仕事はひたすら炭を割ること。炭を割りながら師匠の仕事を見て覚える。

隕石の塊のようなものは「ケラ」と呼ばれる製鉄から生まれた鉄の塊。砂鉄由来の鉄を鋼にする。
古道具(火縄銃の銃身とか)は鍛冶仕事に使う道具ではなく、刀の材料。溶かして「ズク」と呼ばれる鉄の塊を作る。
古道具(火縄銃の銃身とか)は鍛冶仕事に使う道具ではなく、刀の材料。溶かして「ズク」と呼ばれる鉄の塊を作る。


▼試し切り


天籟能の会の協賛会員へのご応募、お待ちしております。
詳しくは、こちらをご覧ください。天籟能の会「協賛会員」のお願い
また、「天籟能の会」、チケットもまだございます。みなさまのご参加をお待ちしております。







